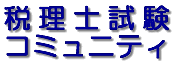makotoさんのプロフィール
| お名前 |
makoto |
| 性別 |
男性 |
| 受験回数 |
3回(官報合格までの受験回数) |
| 合格年度 |
2007年(官報合格年度) |
| 合格科目 |
簿記論 財務諸表論 法人税法 所得税法 消費税法 |
| 利用した予備校 |
TAC |
| 受講形態 |
通学 |
| 受験時の職業 |
会計事務所 |
所得税法について
所得税法について書きます。
・理論はできれば全部覚える
理論については絞ったABランクで40題程度、全部で60題程度だと記憶しております。絞って合格できるなら絞ってもよいとは思うのですが、最近T基準でCDランクから頻出しているため、全部押さえておくのをオススメします。覚えておかなければその時点で一年間が終わりますので・・・。
・本試験は応用理論で差がつく
所得税の試験は正直計算では差がつきません。難しすぎるので・・・。ですから理論勝負の色が濃い科目です。最近の本試験の理論は応用傾向です。それを理論用紙4枚で書くのですから、要点をついた無駄のない解答が要求されます。
要点をついたというのは試験委員が何を聞きたいかというのを適格に捉えてそれに対する解答を概要でずばりと書くのが重要。
無駄のないというのは余計な柱は挙げないこと。4枚と制限されているので大事なことが書けないことになります。
・応用理論はドクターで
・・・三科目連続でスミマセン。所得のドクターは内容がやたらと充実(法人税より分厚い)しているので、ドクター中心でやっていけばいいかなと思います。
ここで重要なのは学校での対策はほぼないということです。Tの上級演習、Oの実判はもちろん、TOそれぞれの直前対策にいたっても理論はべた書きがほとんどです・・・。
よってドクターを使って独学でどれだけやれるかというのが合格に向けての重要な要素となると思われます。
ただ所得のドクターを全部こなすのは結構きついかもしれません(資産損失関係の柱挙げだけでもものすごいことになります・・・)がそこは頑張りどころです。
できればドクター固有の理論まで押さえておきたいところです。
・計算は基礎を正確に
計算に関しては上記のとおり本試験ではあまり差がつかないため人並みにとれればいいのかなと思います。簿記論と同様簡単なところは落とさないように。
・直前期から問題がガラリと変わります
はっきりいってTの基礎答練以前と応用答練以後では科目が変わったのかというくらい問題が激変します。計算で「こんなの知らないと無理」というのがわんさか出てきます。
復習はしっかりするのが原則ですが、できればその問題をしっかり解けるようになるのだけではなく、どういう理屈でそうなるのかを重点的に復習できればいいのかなと思います。
同じ問題はおそらく出ないでしょうけど、普段やっているやっていないでは本試験問題でのアプローチが違ってきます。たまたま取れて超有利になることがある科目なので、本試験でも時間があればチャレンジする姿勢はあったほうがいいのかも。時間との兼ね合いですけど。
以上です。
makotoさんの合格体験記
makotoさんの合格体験記をご紹介いたします。
makotoさんの合格体験記(1) 簿記論について
makotoさんの合格体験記(2) 財務諸表論について
makotoさんの合格体験記(3) 消費税について
makotoさんの合格体験記(4) 法人税法について
makotoさんの合格体験記(5) 所得税法について
makotoさんの合格体験記(6) 消費税電卓について
makotoさんの合格体験記(7) 減価償却の按分月数について
makotoさんの合格体験記(8) 所得税額控除について
makotoさんの合格体験記(9) 理論集の条文番号について
makotoさんの合格体験記(10) 消費税の交換の仕訳について
makotoさんの合格体験記(11) 所得税の譲渡所得の下書き用紙について
makotoさんの合格体験記(12) 留保金課税の計算について
makotoさんの合格体験記(13) 実質的に債権とみられないものの額について
makotoさんの合格体験記(14) 理論詰め込みGWウィーク
makotoさんの合格体験記(15) 試験までに確認したほうが良さそうな点(各科目毎)
makotoさんの合格体験記(16) 求められていること
makotoさんの合格体験記(17) 来年確実にしとめるためには・・・(本試験後について)
スポンサード リンク
|