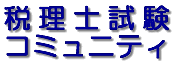makotoさんのプロフィール
| お名前 |
makoto |
| 性別 |
男性 |
| 受験回数 |
3回(官報合格までの受験回数) |
| 合格年度 |
2007年(官報合格年度) |
| 合格科目 |
簿記論 財務諸表論 法人税法 所得税法 消費税法 |
| 利用した予備校 |
TAC |
| 受講形態 |
通学 |
| 受験時の職業 |
会計事務所 |
簿記論について
簿記論の勉強などについて受験時代に思ったことを箇条書きにしてみます。
参考になれば幸いです。
・基礎的な問題を繰り返して解く
いきなり月並みなことで申し訳ありません。
ただ簿記論の本試験は簡単な問題と難しい問題の落差が激しいのが特徴です。難しい問題を捨て簡単な問題を落とさないのがセオリーになると思われます。
また基礎的な問題を何回も解くことにより自信がついてくるのもいいところ。2〜3回やると満点もとれるようになりますし、数字を合わすことができることに楽しみを見出すことができるようになると勉強も楽しくなってきます。
・過去問を重視する
なぜ重視するかというと、本試験と学校の問題の乖離が激しいと思うからです。特に消費税。第3問はほぼ消費税が絡んでくるにもかかわらず、学校ではあまり重視されていないような気がします。
あとは取捨選択の練習です。学校の問題では難易度向上をボリュームに頼りがちあまり練習できないです。目安としては1仕訳以内に解けるものを優先するといいかもしれません。特殊商品売買とかでも即座に捨てるのではなく1仕訳で解けるところはせこくとっていく姿勢が大事なのかも。
・逆進問題を重視する
取捨選択も重要ですが、本試験ではT勘定の集計も重要だと思います。過去問見てもよくでてますし。売掛金やら受取手形やらの集計は合わない可能性は高いですが、合わすと大きなアドバンテージです。
T勘定の集計能力を高めるには逆進問題が一番かなと個人的に思います。問題集にあったらしっかりと何度も解いてみましょう。
・解く順番は柔軟に
私はだいたい第3問から解いてました。1・2問を解いて残り時間が少ない時点であのボリュームの問題にとりかかるのはパニックになる可能性が高いので、余裕のあるうちに第3問で取れるところを探して解いて1・2問にとりかかってました。ただ得意分野が1・2問で出題されていると1・2問から解くこともありましたしそこは柔軟に対応したいところです。
・最後まであきらめない
これは本試験でのことです。ほぼ間違いなく量、内容ともに絶望的な問題を目の当たりにすることになると思います。それでもあきらめずに解くことが重要です。あきらめそうになったら深呼吸してみたりして。私は最後の30分で10点くらい稼いだ記憶があります。
以上です。ちょっと冴えない内容ですね・・・スミマセン。
受験は3年前なのでちょっと変わっているところがあるかもしれません。
makotoさんの合格体験記
makotoさんの合格体験記をご紹介いたします。
makotoさんの合格体験記(1) 簿記論について
makotoさんの合格体験記(2) 財務諸表論について
makotoさんの合格体験記(3) 消費税について
makotoさんの合格体験記(4) 法人税法について
makotoさんの合格体験記(5) 所得税法について
makotoさんの合格体験記(6) 消費税電卓について
makotoさんの合格体験記(7) 減価償却の按分月数について
makotoさんの合格体験記(8) 所得税額控除について
makotoさんの合格体験記(9) 理論集の条文番号について
makotoさんの合格体験記(10) 消費税の交換の仕訳について
makotoさんの合格体験記(11) 所得税の譲渡所得の下書き用紙について
makotoさんの合格体験記(12) 留保金課税の計算について
makotoさんの合格体験記(13) 実質的に債権とみられないものの額について
makotoさんの合格体験記(14) 理論詰め込みGWウィーク
makotoさんの合格体験記(15) 試験までに確認したほうが良さそうな点(各科目毎)
makotoさんの合格体験記(16) 求められていること
makotoさんの合格体験記(17) 来年確実にしとめるためには・・・(本試験後について)
スポンサード リンク
|