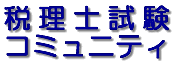「場合」・「とき」・「時」
「場合」は、要件、前提等を表すときに用います。
「とき」も、要件、前提等を表すときに用います。「場合」の違いは、「とき」を用いるケースとして多いのは、「○○の場合において××のとき」のように、要件等が2つ以上ある場合が多いようです。
「時」は、時点を表します。このように、税法の用語としては、「とき」と「時」を明確に使い分けます。
「者」・「物」・「もの」
すべて「もの」と読みますが、税法を覚える際には、それぞれ「しゃ」・「ぶつ」・「もの」と区別をすると覚えやすいようです。
自然人や法人をあらわす場合に「者」を用い、
動産や不動産等の有体物をあらわす場合に「物」を用い、
(1)人格をもたない行為主体や、(2)無体物をあらわす場合、(3)人格や物をあらわす以外の場合に「もの」を用います。
「及び」・「並びに」
「及び」・「並びに」はどちらも「○○と××」というような使い方をしますが、使い分けとしては、結びつきの強さで分けます。
すなわち、「及び」は、併合の意味で使い、並列する語句が二つのときには、その接続に用います。三つ以上のときには、始めの2つの用語の間を「、」で区切り、最後の語句を繋ぐのに「及び」を用います。ただし、最後の語句の後ろに「など」や「その他」などの用語が続く場合には、「及び」を用いることはできませんので注意が必要です。
一方、「並びに」は、併合の意味で「及び」を用いて並列した語句を、更に大きく結び付ける必要があるときに、その接続に用います。使い方としては、例えば、「A及びB並びにC及びD」となります。
「又は」・「若しくは」
「又は」・「若しくは」は「○○か××」というような使い方をします。
両者の使い分けは、上記の「及び」・「並びに」と同じで、結びつきの強さで分けます。
すなわち、「又は」は、選択の意味で使い、並列する語句が二つのときには、その接続に使い、三つ以上のときには、始めの2つの用語の間を「、」で区切り、最後の語句を繋ぐのに「又は」を用います。ただし、最後の語句の後ろに「など」や「その他」などの用語が続く場合には、「又は」を用いることはできませんので注意が必要です。
「若しくは」は、選択の意味で「又は」を用いて並列した語句を、更に選択の意味で分ける場合に用います。使い方としては、例えば、「A若しくはB又はC若しくはD」となります。
「看做す」・「推定する」
「看做す」は、本来そうでないものを法律上はそうであるものと同一に取り扱い、その例外や反証を認めない場合に使います。
一方で、「推定する」は、反証によって例外を認める余地を残し、ある一定の事実に同一の法律効果を認めようとする場合に使われます。
「科料」・「過料」
「科料」は、刑法で定められている財産刑であり、罰金より軽い刑罰です。
「過料」は刑罰ではなく、行政上の義務を履行させる心理的強制として科せられるもので行政罰、秩序罰とも呼ばれます。
ともに発音上同じため、文字で表示しないときは、両者を識別するため、「科料」を「とが料」、「過料」を「あやまち科」として訓読しています。
「以下」・「未満」
「以下」はその数字を含む下の数字の範囲のことです。
一方で、「未満」はその数字を含まない下の数字の範囲のことです。
「以上」・「超える」
「以上」はその数字を含む上の数字の範囲のことです。
一方で、「超える」はその数字を含まない上の数字の範囲のことです。
「以前」・「前」
「以前」はその日付を含む期間のことです。
一方で、「前」はその日付を含まない期間のことです。
「以後」・「後」
「以後」はその日付を含む後ろの期間のことです。
一方で、「後」はその日付を含まない後ろの期間のことです。
「直ちに」・「遅滞なく」・「速やかに」
どれも、時間的にすぐという速さを意味しますが、
「直ちに」という使い方が最も速く、何があってもすぐ即座にやらなければならないという場合に用います。
「遅滞なく」は、他に何か正当な理由などがあるときは、多少の遅滞は認めるという程度の速さに場合に用います。
「速やかに」は、できるだけ速くという訓示的な意味の場合に用います。
「科する」・「課する」
ともに一定の義務で負担を負わせる場合に用いますが、以下の点で両者は異なります。
「科する」は、罰金、過料など刑事罰や行政罰をかける場合に用います。
一方で、「課する」は、税金や分担金の支払いなど刑事罰や行政罰でない義務の負担を命ずる場合に用います。
スポンサード リンク
おすすめ書籍
|