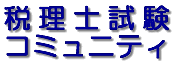
|
ホーム | サイトマップ |
|
|
|
選択科目の選び方ホーム > 選択科目の選び方試験科目についてでも書きました通り、合計5科目の科目合格制度の税理士試験において、選択科目が存在します。 スポンサード リンク |
選択科目の選び方
選択科目では、相続税法と消費税法が人気となっています。 この2科目は、実務に直結する科目と言うことで、両方学習していると、合格後に税理士として活躍する時に役に立つと言われています。 特に、消費税は比較的新しい試験科目ですが、実務に直結するだけでなく、身近な税金でもあり、さらに、ボリュームの少ないことから、特に人気が高くなっています。 また、国税徴収法や酒税法などはボリュームが少ないため、働きながらの受験など、学習時間が多く取れない受験生には一定の人気があります。 しかし、そうは言っても、科目合格率は、どの科目も概ね10%〜15%程度となりますので、ボリュームが少ないから合格しやすい、ボリュームが多いから合格が難しいとは言えないようです。 したがって、科目を選択する際はボリュームの多少だけではなく、それぞれの科目の特徴(実務における重要性、出題傾向、科目間の関連性等)も考慮することが必要です。 (なお、プチアンケート 「選択税法、まずどの科目から勉強しますか?または、勉強していましたか?」 も参考にしてみてください。) 科目の関連性を考慮する2科目以上学習する場合には、学習内容が関連する科目を選択することで相互のレベルアップを図ることができます。 簿記論と財務諸表論 法人税法と事業税 所得税法と住民税 所得税法と法人税法 スポンサード リンクおすすめ書籍 |
サイト内検索 「税理士試験」関連検索 「税理士試験」に関連する検索となります。 税理士試験に関連する情報を探したい時にご利用ください。 |
|税理士試験コミュニティ ホームへ戻る|
Copyright (C) 税理士試験コミュニティ All Rights Reserved.