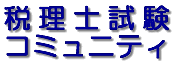科目の選択を考える
11科目中5科目に合格する税理士試験は、科目の選択が重要なポイントになります。
ただし、簿記論と財務諸表論は必須科目であるため選択の余地はありません。
選択必須科目の法人税法と所得税法のいずれか又は両方を含めた税法9科目の中からどの3科目を選択するかが重要となります。
これらの科目選択を考える上では、(1)合格後の実務に役立つか、(2)科目のボリューム、(3)科目間の関連性を考えた効率、(4)計算と暗記の割合、を考慮して決定すると良いと言われています。
(1)合格後の実務に役立つかを考える
税理士試験に合格した後にも、実務で頻繁に使用する科目を選択する方法です。税理士の実務で頻繁に使用する科目としては、
企業向けでは、法人税法と消費税法、
個人向けでは、所得税法と相続税法、
が挙げられます。
(2)科目のボリューム
各科目によって、学習のボリュームは大きく異なります。自分が確保できる学習時間に応じて、科目を選択していく必要があります。
なお、各科目の標準学習時間は試験科目についてをご覧ください。
(3)科目間の関連性を考えた効率
科目によっては、科目間で論点が重複する部分があります。
つまり、重複した部分は効率良く学習できるとともに、学習量の負担も軽減することができます。
なお、科目間の関連性は選択科目の選び方をご覧ください。
(4)計算と暗記の割合
計算と暗記。自分の得意とする学習内容の比重が高い科目を選択すると効率的かもしれません。
なお、各科目の計算と理論の配点比率は試験科目についてをご覧ください。
1年間で何科目受験するかを考える
1年間で何科目受験するか、何年で5科目合格を目指すかは、受験に専念できるなど学習時間を多く取れる人と、働きながらの受験を考え学習時間が多く取れない人とで、方針が変わってくると思います。
受験に専念できる人は2〜3年、働きながらの人は3〜5年で、5科目合格を目指すのが一般的です。
2年で合格を目指す受験生の一般的なプラン
| 1年目 |
・簿記論
・財務諸表論
・選択科目
の合格を目指す |
| 2年目 |
・法人税法or所得税法(もしくは法人税法and所得税法)
・選択科目
の合格を目指す |
3年で合格を目指す受験生の一般的なプラン
| 1年目 |
・簿記論
・財務諸表論
の合格を目指す |
| 2年目 |
・法人税法or所得税法
の合格を目指す |
| 3年目 |
・選択科目
・選択科目
の合格を目指す |
4年で合格を目指す受験生の一般的なプラン
| 1年目 |
・簿記論
の合格を目指す |
| 2年目 |
・財務諸表論
の合格を目指す |
| 3年目 |
・法人税法or所得税法
の合格を目指す |
| 4年目 |
・選択科目
・選択科目
の合格を目指す |
5年で合格を目指す受験生の一般的なプラン
| 1年目 |
・簿記論
の合格を目指す |
| 2年目 |
・財務諸表論
の合格を目指す |
| 3年目 |
・法人税法or所得税法
の合格を目指す |
| 4年目 |
・選択科目
の合格を目指す |
| 5年目 |
・選択科目
の合格を目指す |
一般的な受験生の傾向
(1)簿記論から始める
簿記はすべての基礎となり得るため、税理士試験の多くの受験生は、簿記論の勉強から始めます。
ただし、各科目と簿記の関連性で記載した通り、簿記と関連のない科目もあります。税理士試験を志した時期が1月あたりなどの場合、本試験までの期間を考えると、1年目はボリュームの少ない選択科目を選ぶという作戦も考えられるため、必ずしも簿記論から始めなければならないわけではありません。
(2)簿記論の次は財務諸表論
簿記論と財務諸表論は、同じ会計科目で相互関係が強いため、ボリュームが単純に倍にならず、学習負担が軽減できます。
また、計算部分などは、かなり共通するため、効率的に学習できます。財務諸表論は、簿記論と同時に学習するか、簿記論を受験した次の年に学習するのが一般的です。
スポンサード リンク
おすすめ書籍
|