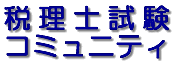だるまさんのプロフィール
| お名前 |
だるまさん |
| 性別 |
男性 |
| 現在の年齢 |
28歳 |
| 受験回数 |
3回 |
| 合格科目 |
H18年度…簿記論(不合格)、財務諸表論(合格)
H19年度…簿記論(合格)、消費税法(不合格)
H20年度…消費税法(不合格)、固定資産税(合格)
現在、残り2科目の合格に向けて、法人税法と消費税法を勉強中。
|
| 利用している予備校 |
TAC |
| 受講形態 |
通学 |
| 受験時の職業 |
会計事務所勤務 |
2.財務諸表論の勉強方法
最初に
多くの科目が設けられている税理士試験ですが、近年は財務諸表論の合格率が一番高い、という状態が続いています。
税理士試験を受験する人の多くが会計科目(簿記論・財務諸表論)から始めることと思いますが、思うに、あまり入り口(簿記論・財務諸表論)を狭くすると、税理士試験の受験人口が確保できなくなる恐れがある、との懸念から、会計科目の合格率を税法科目より高く維持しているのでは、と思います。(あくまで個人的な意見です)
合格率が10%を割り込む科目がある中、安定して15〜20%の合格率の財務諸表論に何度もつまづいているようでは、かなり先行き不透明と思ってください。しかも、「簿記3級に受かったから申し込んでみた」といった記念受験組が、税法科目より多く含まれていると想像されての高い合格率です。厳しいことを言いますが、この科目にハマってるようではいけません。
計算 - (1)基本的な勉強方針
財務諸表論の計算は、簿記論ほど難解な仕訳、問題構造にはなっていません。
簿記論は「会計処理の知識」が問われている一方、財務諸表論は「計算書類の作成・表示方法」が基本的に問われているからです。
よって、簿記論と平行で勉強されている方は、簿記論の問題を練習すれば財務諸表論の計算には基本的には対応できます。
あとは、注記、試験委員対策のため、3日に一度程度、演習や模試の総合問題を解きなおせば十分だと思います。
計算 - (2)注記や科目名は全部書く
最近の試験では注記は出ていないようですが、解答用紙に注記や長い勘定科目名を書く時、面倒くさがって省略しない方が良いと思います。
本番は想像するよりも緊張するものです。普段なら何でもないことが、緊張のせいで書けない・思い出せないということがあります。
ただ、体に染み付いていることならば、そのまま自然と出てきます。
面倒でも、体が覚えるくらいまで何度でも書いてください。それを書いたところで、何十分も勉強時間が減るわけでもないですから。
計算 - (3)ケアレスミスをしない
財務諸表論の計算問題は平易なレベルの仕訳が多いですが、その分、わりと高得点が要求されます。
ということは、ボロボロとミスから点を取りこぼしているようでは合格圏内に入れません。
スピードも大事ですが、それに増して必要なのは正確性です。
理論 - テキストをとにかく読む
自分は3月まで一般企業に勤めていた関係で仕事が早朝から深夜に及び、勉強時間がほとんど取れませんでした。
4月からの4ヶ月間で合格レベルに持っていくには、予備校のテキスト以外のものに手を伸ばすヒマがなく、救いを求めて相談した先生にも「テキストをとにかく読んでください」とのアドバイスを頂きました。
そこで、テキストの太字の部分(キーワードや要件になっている部分)をマーカーで引き、毎日最低100ページくらいは読んでいました。
用語をそのまま解答させる問題は自分の言葉では書けませんが、財務諸表論の理論は「条文通りに書く」ことは求められていません。何度も何度も読めば、例えば「引当金の要件」をテキスト通りの文言でなくても何が書いてあったか思い出せるようになりますし、思い出せることは本番でも書けます。また、テキストを読みこなすことが内容理解につながります。
地味ですが、これが一番効果的な勉強方法だと思います。
だるまさんの合格体験記
だるまさんの合格体験記をご紹介いたします。
だるまさんの合格体験記(1) 税理士試験への取り組み方
だるまさんの合格体験記(2) 財務諸表論の勉強方法
だるまさんの合格体験記(3) 簿記論の勉強方法
だるまさんの合格体験記(4) 固定資産税の勉強方法
スポンサード リンク
|